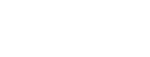blog article
いつの間にか昔の自分が戻ってきていた件
今日は楽しい、そして興味深い発見が自分にあったのでお話ししたいと思います。
結論から言うと、
ふと気づいたら中学生以前の自分が戻ってきていた
ということなのですが、具体的に言うと、
音楽を聴きながら数学の問題を解いていた
と言う話です。
これだけでは意味が分かりませんね。
順を追ってご説明いたします。
中年になって受験の問題に取り組む・・・
いきなりですが私は数学と物理が趣味の変なやつです。
つい先日、勤務先の整形外科のスタッフの息子さんが大学の数学科を目指しているときいて、
「実は私も数学が趣味なんですよ」
といったところ、その息子さんは数学の問題を解くだけでなく問題を考えることが好きらしく、「自分の考えた問題を持ってきていいか」、とそのスタッフの方(母親)を通じて私に言ってきたのです。
さすがに受験数学などは何年も問題すら見たことがないので、多少の不安はありましたが、
「受験勉強の妨げにならないのなら、自信はないけどいいですよ」
とお答えしたところ本当に問題を持ってこられたのでした。
一目見てどういう意図の問題かはなんとなくわかりましたが、受験の問題は様々なところに落とし穴が仕掛けてあるのが常ですし、どのレベルの問題かがわかっていると題意もわかりやすく、正解に結びつきやすいと言う、いわゆる「受験のテクニック」と言うものがあります。また問題自体の題意や解答への組み立ても大学ごとに傾向があって、実際に問題を解く場合はそれを読み取ることも大事になってきます。
私は計算間違いや勘違いが多い(一言で言うと「おっちょこちょい」です)人間なので、じっくり問題にあたるべきだったのですが、正直そこまでじっくり考えるのもしんどかったのもありますし、一回目は、あまり考えずに、まあ、こんなもんだろうと思って提出したところ見事に玉砕(笑)してしまったのでした。
本当は彼の邪魔になってもいけないので、一回だけで終わろうと思ったのですが、ここでやめたら大人の沽券に関わるということで、彼の邪魔にならないのならば、これ以降も持ってきてもらっていいよと返事をしたところ、なんと2問目がきたのでした・・・。
正直なところ、1問目は間違えてしまったのでバカにされているだろうなと思ったのですが、彼は本当に数学が好きなのでしょうね・・・。
2問目はいわゆる三角関数の問題で、正直なところ加法定理(数学苦手だった方はすみません・・・)しか覚えていない自分としては、加法定理とそれから派生する定理を一旦全て書き出し、すっかり忘れていた他の定理もなんとか思い出し、準備を整えてからのチャレンジとなりました。
実は1問目のときもそうだったのですが、私にとっては数学を考える行為そのものが結構楽しいのですね。
最近自分が趣味としてやっていた数学は全然別の分野で、受験の数学とは全く違うものだったので、高校数学の問題を解いていると昔のことを思い出すような感じがして結構楽しい。
仕事帰りの電車の中で一通り考えて、2つの設問のうち1問目はすぐに解けたのですが、侮ってはいけません。一回めの失敗を繰り返さないように、何か勘違いをしていないかチェックしようと家に帰ると、妻がいい感じのロックを聴きながら仕事をしています。
私は一緒にコーヒーとおやつを食べながら、もう一度書きかけの回答にミスがないか、また、別の回答がないかをチェックしていたのです。

1問目のチェックを終え、2問目に取り掛かかります。2問目も答えは分かったのですが、その証明がちょっと甘い感じがして、じっくり考えてみます。
その時、ふと気づいたのです。
「あれ?俺、音楽結構マジで聴きながら、数学の問題もしっかり考えているよな・・・?」
「この感覚って、小学校とか、中学校以来じゃね・・・?」
どう言うことか説明しましょう!
ながら〇〇が大好きだった子供の頃
私は中学生の頃ぐらいまでは物覚えがかなり良い方で、今でもはっきり覚えているのですが、小学生6年生の時に、宮沢賢治の「アメニモマケズ」を暗記すると言う授業があった時、数分で暗記(クラスで一番でしたが)して先生を驚かせたこともありました。
中学生になっても、苦手な英語はテスト範囲の教科書をほぼ丸暗記したり(良い勉強法とはいえませんが・・・)して凌いだりしていたのでした。
中学生の頃はテスト前しか勉強はしませんでしたが、その時の勉強の仕方というのが、常に音楽を聴きながら・・・、と言う方法でした。
「ながら〇〇」は集中力が落ちるのでダメ、と言うようなことが当時よく言われていましたが、自分にとってはむしろ長時間勉強しても良い具合にリラックスできると感じていましたし、とにかくその方が結果的に暗記力も理解力も良いことは明らかだったので、そういう勉強法をとっていたのです。
ところが高校生になると暗記力が途端に落ちたのです。
要求される暗記の量が増えたというのもあったのでしょうが、以前のように頭に入ってこない上に、理解力もだんだんと落ちていったのを覚えています。
自分ではどう言うことなのかわけがわからず、毎日モヤモヤしたような感じで過ごしていたような気がします。
そして、もう一つ今回の話題である「音楽を聴きながら勉強」と言うことが全くできなくなってしまったのです。
むしろ音楽を聴いている方が集中できない。そしてなぜなのかそれが自分にはわからない。
私は常に音楽を聴いていないと生きていけない人間です(笑)
それが勉強に時間を取られて音楽が聞けなくなってしまうと、ストレスが溜まってしまって、なんとなくどよーんとした気分になってしまうのです。
その後一時的に成績は上がったのですが、どうにもこうにも勉強する気が全くなくなってしまい、結局私は高校中退ということになってしまったのでした・・・。
これが、ゆる体操・運動科学的にどうなのかと言うとことをお話しします。
もしこのサイトに来られたのがこの記事が初めてで、「ゆるむ」ということをよくご存知ない方は以下の記事をご覧ください。
よく読まれている関連記事
体が固まると学習効率も落ちる
上の記事を読んでいただければお分かりかと思いますが、私が高校生になって学習能力、記憶力ともに落ちた原因は、まず第一には、体が固まってしまった、ということがあります。
念のためにゆるむという効果をご存知ない方のために簡単に申し上げますと、例えば運動の場合は体が固まってしまうと思うように体を動かせないのでパフォーマンスは落ちます。
同様に思考活動でもパフォーマンスは落ちるのです。
これは大切な試験でも、一時的にせよ緊張して体が固まった状態では良い結果が出ないと言うことからもお分かりだと思います。
当時の私が体が固まる理由は色々あったと思うので、ここでは一つ一つ理由を挙げることはしませんが、結局のところ中学生の時まではそれなりにゆるんでいた体が高校生になって一気に固まり、記憶力、理解力ともに落ちたと言うことにつきます。
そして、ながら勉強の件で言うと、ながら〇〇というのは言うなればマルチタスクです。
マルチタスクというのはゆるんでいなければできないことです。
なぜならば、何かに真面目に取り組む時は、当然集中力が必要ですが、このサイトで何度も触れているように集中力にはゆるんだ集中の仕方である緩解性意識集中と、力んだ意識の集中の仕方である緊張性意識集中の2種類があります。
緊張性意識集中はいわば「固まった集中」ともいえます。これは自分の顕在意識のみが活性化している状態で、この状態になると他のことが見えなくなってしまいます。
それに対して緩解性意識集中は「ゆるんだ集中」です。潜在意識と顕在意識がバランスよく活性化している状態なので、自分が顕在意識で見えていないところも潜在意識が色々フォローしてくれるような状態なのです。
また、脳は一部分に負担をかけるような使い方をするとすぐに固まってしまいます。例えば記憶するときに、記憶しよう記憶しようと思うだけでは大して記憶力は良くなりません。
これは体も同じですね。一部分だけを鍛えても全体のパフォーマンスは良くならないのと同じことです。
記憶に限りませんが、学習する場合は暗唱して、手で書いて・・・、と体の他の部分も一緒に使った方が、結果が良くなることは皆さんもご存知のことと思います。
「全脳的」とも言いますが、何かを行うとき、脳の様々な部分を統合的に使った方がパフォーマンスは上がり、様々な学習において効果・結果は良くなるのです。
実はゆる体操が擬態語をつぶやいたり、ダジャレを言ったりしながらやるようになっているのもこの事実を織り込んでのことなのです。
次にこのことについてご説明いたします。
ゆる体操はそもそもマルチタスクな体操である
子供は擬態語やダジャレが大好きですが、真面目にこの事を説明しますと、まず擬態語は動作や動作の質を表す言葉です。プラーンとかユッタリとかはまさしくそうですよね。
腕を「プラーン」と振るとき、運動自体は「腕を振る運動」なのですが、「プラーン」と言うことにより、「プラーン」といった擬態語で表現される「運動の状態」を感知する脳の部分も強く働きます。これが結局のところ複雑な脳活動を生み出すことになるのです。
一方でダジャレは全く違う分野のものを掛け合わすことといえます。
例えば体の部位を表す名詞である「上腕」と音が響くときの擬態語「ジョワーン」は意味的には全く関係がありませんが、その二つを関連つけることにより、(ただ単に「上腕を動かす」というよりも「上腕をジョワーンとゆるめる」と言った方が)脳はより複雑な処理を自然にしようとするのです。
物理や数学の世界では全く違う分野の関連性が発見されたとき、それまでわからなかった法則や定理が発見され、その世界全体の認識が一気に進むことがあります。
言うなれば運動科学でのダジャレへの認識は、そういった高度な世界への入り口だと私は非常に真面目に考えています。
(受けを狙って言う「親父ギャグ」は最悪ですけどね・・・)
元々誰でも子供の頃は脳の連関性が高いので、ダジャレとか擬態語が大好きなのです。
このようにゆる体操にはそもそも脳を連関させる作用を強く促す仕組みが組み込まれています。
そして脳の様々な部位の連関性とゆるむこととは相関関係があります。
ですからゆる体操をしていると、自然とマルチタスク能力が上がってきます。
身近なことでいうと、私は最近料理をするとき、
「出来上がったときにはほとんど台所が片付いている」
ということができるようになりました。
そもそも食べた後は眠くなるので片付けがめんどくさいから始めた事なのですが、いつの間にかできるようになったのです。
要するに料理しながら片付けているのですね。
料理自体はそもそもマルチタスクの部分がありますが、最近私は台所仕事全般に関してはマルチタスク能力が上がったと思っています。
さて、話をもとに戻しましょう。
なぜ私が高校生になって「ながら勉強」ができなくなったのか。
なぜ今それがまたできるようになったのか。
もうお分かりですよね。
子供の頃の感覚が自然と甦る
子供は元々マルチタスク能力が大人より高いのですが、中学生までの私はおそらく、学習で使う脳と音楽を聴く脳がそもそもリンクしているような性格・性質で、曲から聞こえてくるメロディ、リズムが記憶力、読解力を刺激して、より効果が高まるというような脳の機能がそもそもあったのだと思われます。
そして若い頃はそれなりにゆるんでいた(あくまで「それなり」ですが)のでしょう。
しかし高校生になって急激に体が固まり、それなりながらも持っていた能力が次第に失われ、以前できていたことができなくなってしまったのだと考えられます。
そして現在、長年ゆる体操に取り組んだ効果として、それが少し甦ってきたのでしょう。
また、その時の自分の状態ですが、非常にご機嫌である意味「幸せ」とも言える気分だったことを覚えています。(おやつを食べていたせいかもしれませんが・・・)
自分が好きなことなのでご機嫌なのは当然なのですが、ある種の幸福感を伴うということは「それなり」にゆるんでいたのでしょうね。
あ、言っておきますが、受験のレベルの問題と言っても、問題そのものはそんなに難しいものではないんですよ。
おそらく「良問」レベルのものだと思います。
ゆる体操をやっていると自然に色々な変化がおこってきます。それはゆる体操が潜在意識にアクセスするようにできているからです。
潜在意識なので主体としての自分は気づかないことが多いのです。
でも、それがまた楽しいのですよね。
ちなみに2問目は正解でした。今は3問目を提出したところです(笑)
しかし記憶力に関しては現在は普通以下のトホホな状態です・・・。これもそのうち改善されるといいんですけどね。
教室でゆる体操を学びたい方はコンテンツページへ
ご自宅からゆる体操を学びたい方へ動画配信中
中田ひろこがTwitterでゆる体操や体のことについて呟いていますので、よかったらフォローしてくださいね。
中田ひろこ@ゆる体操